夏目漱石といえば、ご存知のように、近代社会の形成期において、人間と人間の確執を見詰め尽くした作家です。人間同士の憎しみや嫉妬など、様々な煩悩を見詰め続けることは苛酷な作業であり、それが彼の精神や肉体に過度なストレスを強いたことは、想像に難くありません。
そのはての破綻。漱石の読者なら誰でも知っている、胃潰瘍による大吐血、いわゆる「修善寺の大患」です。彼自身が述懐しているように、30分ほどは実際に死んでいたということですが、次の句は文字通り、生死の境を彷徨ったのち、復帰直後の句です。
生きて仰ぐ空の高さよ赤蜻蛉
日常に戻って、ふと仰いだ空の抜けるような青さ、普通は「空の高さ」など誰も気にかけておりません。まして、エゴイスティックな人間社会の生態を己れの内外に見つめ、相対立する人と人が織りなす相対の世界を表現してきた漱石こそ、『門』という作品に象徴される絶対への希求は常にあったとしても、実際に「空の高さ」を仰ぐ余裕などはなかったにちがいありません。
思えば、彼の作家活動は『草枕』冒頭の、「知にはたらけば角が立つ、情に棹差せば流される、意地を通せば窮屈だ、兎角人の世は住みにくい」という感覚に発するものといって良いでしょう。なるほど、世間というものは、えてして不条理なものだし、それ以上に、己の中にある貪、瞋、痴の三毒(仏教でいう、人間に苦を強いるむさぼり、いかり、おろかさ)も執拗に彼を責め立てたに違いありません。しかし、「住み悪いとのみ観じた世界に忽ち暖かな風が吹いた」という漱石は、同時期前句と同様次のような句も作っております。
肩に来て人懐かしや赤蜻蛉
と、ここでは一たび死=空(くう)をくぐり抜けることで、はるか上にある「空の高さ」に気づいただけでなく、この空の高さの下ではみな平等であり、善意をもって平和裡に事が推移していることの気づきといって良いでしょう。彼はまた、次のようにも言います。
病に生き還ると共に、心に生き還った。余は病に感謝した。また 余のために是程の手間と時間と親切を惜しまざる人々に謝した。さうして願わくば善良な人間になりたいと考えた。
無論、ここでの漱石の心境の変化はそれほど深いものではなく、一方でいわゆる「則天去私」を求めつつも、結局は反省に近いものでしかなかったであろうことは疑えませんが、少くとも彼が「空の高さ」への気づきを通して、肩にとまった赤蜻蛉に「人懐しさ」を感じる柔軟さを獲得していることは、注目に値すると思われます。
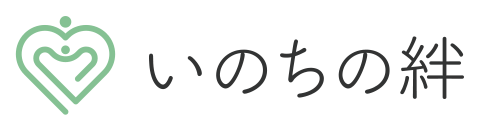



コメント