何回か前のブログで、相対立する語をつなげた熟語が、その向こうに対立を超えた世界を開示する不思議に触れましたが、むしろ日本人は、このような論理性をひねり、逆説的に世界の、あるいは人間の深みに、真相を探ってきたふしがあるのです。たとえば、西田幾多郎には「絶対矛盾の自己同一」という有名な言葉がありますが、この「矛盾」と「同一」の向う、あるいは深みにこそ、日本文化が古来求めてきた真理があるように思われます。やはり、先のブログで述べましたように、たとえば「月影」という言葉がありますが、光と闇という根源的に対立する語もやはり、「矛盾」と「同一」を超えた日本人の魂の底流に、垂鉛をおろすに有効であると思われます。江戸時代の俳人、加賀の千代女にも光と闇をテーマとした、有名な次の一句があります。
川ばかり闇は流れて蛍かな
言うまでもなく、闇と蛍(光)はそれぞれ死と生を象徴していると受けとめることで、この句の奥行きも格段に深まりますが、この句の眼目は、あたかも永遠(死)と刹那(生)をつなぐように、その闇を川、すなわち底暗い命が流れ、しかも闇の静寂(死)を川の音(生)が破るというような見事な構図。まさに日本人独特かつ不気味な死生観を、ありきたりの夏の風物詩にのせた秀句といって良いでしょう。そして、闇と光のやはり不気味な対比を詠むものに、現代俳人の折笠美の次の句があります。(句集『死出の衣は』)
逢いみれば風匂い生きおれば闇匂い
闇よりも濃い闇が来る燭持てば
折笠さんは俳句を作りながら新聞記者として、活躍しておりましたが、たしか四十路の後半、突然全身の筋肉が失われていくALSという難病に見舞われます。手足は無論、呼吸も筋肉作用ですから、人工呼吸器を離せず、声もだせない病床で、わずかに動かせる目と
唇を奥さんが読み取り、文字化する形で句作が続けられたのです。 上の第一句の上句は、見舞いに来た娘が連れてきた風の匂いを感じ、下句は、愛する家族が去り、一人で死の孤独と対峙しなければならない闇を匂いとして感じとっているのです。いうまでもなく、この「匂い」は五感の一部、すなわち嗅覚だけで感じている訳ではありません。
第二句と同様、無論、「燭持」つことは、家族と過ごす一瞬の幸せな時。しかし、それが一瞬にして去ったあとの一段と深い闇と孤独は、俳人としても死の床の上で初めて味わったにちがいありません。人は誰しも、本当はこの両極の間を行き来しているだけなのですが、「健康」という幻想の皮膜ゆえに、それに気づかないだけなのです。
残り少ないいのちを一刻一刻すり減らしている折笠さんのような人だけが、その両極を生き切ることができたのは、言うまでもなく
彼の繊細な感性が適切な言葉に言いとめる詩心があったからですが、彼に闇を直視する勇気がなければ、そしてそのような彼を温かく見守る家族との幸せがなかったら、決して結実することはなかった奇跡にほかなりません。
それは多分、光は闇あってこそ輝き、闇も光あってこそ深くなるということで、それが稀に「漆黒の中に色艶」をみるような作品を生み出してきたのです。
彼の句に季語が脱落し、定型すら無視されているのは、既に彼が約束事によって成り立つ定型(日常)社会から脱落いるから、いって良いでしょう。
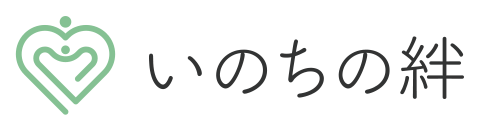



コメント