こうして江國滋氏は逝きましたが、残る家族はどのように彼の死と和解したのでしょうか。無論、家族の細々として看病の記録などには興味がありません。むしろ死を前にした氏の句作が、彼の生きざまを詩的に昇華したように、見送る側にもその最期をみつめ尽くし、納得する詩的昇華のプロセスがあるとすれば、その生死を媒介として向かい合った、究極の姿が見たいと思うのです。
江國氏のお嬢さんは作家香織さんですが、彼女に、父との人生を煮つめ尽くしたような、次の詩があります。題して「父に」。
病院という
白い四角いとうふみたいな場所で
あなたのいのちが少しずつ削られていくあいだ
私はおとこの胸のなかにいました
たとえばあなたの湯呑みはここにあるのに
あなたはどこにもいないのですね
むかし
母がうっかりと茶碗を割ると
あなたはきびしい顔で私に
かなしんではいけない
と、言いましたね
かたちあるものはいつかは壊れるのだからと
かなしめば ママを責めることになるからと
あなたの唐突な
ーそして永遠のー
不在を
かなしめばそれはあなたを責めることになるでしょうか
あの日
病院のベッドの上で
もう疲れたよ
と言ったあなたに
ほんとうは
じゃあもう死んでもいいよ
と
言ってあげたかった
言えなかったけど。
その少しまえ
煙草をすいたいと言ったあなたにも
ほんとうは
じゃあもうすっちゃいなよ
と言ってあげたかった
きっともうじき死んじゃうんだから
と。
言えなかったけど
ごめんね。
さよなら
私もじきにいきます
いまじゃないけど
ここには、一見つき放したような親子関係が描かれているように見えますが、実はとかく私たちが安易に執着するヒトやモノへのこだわりを超えたギリギリの愛の位相が開示されているのです。めそめそとした湿っぽさが嘘だというのではありません。それでも、この父にしてこの娘ありといいましょうか、感情を極力抑制して、彼女は涙が乾いたあとに残る愛をみつめようとしているのです。
この詩の重心は、二度繰り返される「言えなかったけど」にあります。無論、愛ゆえの無言にほかなりませんが、彼女はこの心に残るオリをテコにして、父の永遠の不在を、今この詩で客観化し、相対化しようとしているのです。執着や感傷は所詮己の自我の写し絵にすぎず、それは彼女の父がたぶん後ろ姿で示した諧謔に違背し、諧謔に象徴される「粋」から転落するものでしかない、ということでしょう。父も娘も、別れのもつ厳粛な真実を、安っぽい言葉や涙で汚したくなかったのです。
この父の句にも娘の詩にも、なまの感情やことばの持つ安っぽさがありません。むしろ父はギリギリの言語表現で、自分の生や家族への想いを断ち、娘はこの詩で父や母とのこれまでの執着に別れを告げているのです。生と死を受け入れた心には、一つ一つの言葉が断念の響きを放っているように思われます。
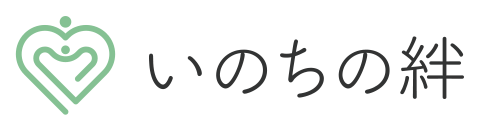



コメント