『平家物語』は平家一門の盛衰を描いた軍記物語ですが、歴史教科書と違い、単に事件を羅列するばかりでなく、滅びゆく人々の希望、絶望、悲哀といった、現代にも通じるテーマと深く関わっており、義経や維盛の最後など、読みてにも身につまされる体験に誘い込みます。
なかでも、「足摺」と「有王島下り」における俊寛の物語には、生と死について改めて深く考えさせるものがあります。
1177年、平家打倒の「鹿谷の陰謀」が発覚、藤原成親、平康頼と東山法勝寺の俊寛は薩摩の南島の鬼界が島へ流刑になります。そこは島人といえば「色黒うして牛の如し、身にはしきりに毛生いつつ、云う言葉も聞きしらず」とあり、島の中央の活火山から絶えず硫黄が流れ出ているので作物も育たない不毛の地。
やがて、清盛の娘の徳子の安産を願って、成親と康頼には恩赦が下りますが、目をかけてやったのにという清盛の俊寛に対する怒りは消えず、彼のみ島に残されることになります。
島に着いた役人の示す赦免状に彼の名前はない。驚愕した俊寛h船に取りすがり、「是のせてゆけ、見してゆけ、とおめきさけべども、漕ぎゆく船のならいとて、跡は波ばかりなり」とあります。俊寛は砂浜に打ち伏して、満ち来る潮に足を洗わせながら、身動き一つしない。しかし、彼の心は生と死の間で揺れ動き、必ず清盛を説得し、迎えに来るからという成親の言葉を信じて、改めて生への執着を燃やすのです。
一方京では有王というかって俊寛に使えていた若者が主俊寛のみが不赦免との知らせに驚き、隠れ住んでいた娘の手紙を携えて、やっと鬼界が島にたどり着きます。数日は探しても見つからず、やっと磯の方から、体中に海藻を巻きつけた人影がかげろうのようにおろめきながら出てくるのに出会い、師弟再会を果たします。
やがて俊寛の仮小屋で有王は( )遠島後の京の事情を話しますが、俊寛の兄弟、家来はすべて処刑され、妻と息子と娘は蔵馬に身を隠していたが、6歳になる息子が病死、妻は俊寛不救済の報に悲嘆し、息子のあとを追ったというのです。
こうして、最愛の二人の死は、俊寛の生への執着を断ち切り、以後断食して念仏を称えながら横たわって死に臨むのです。有王も努力すれば二人分の食料を確保することができましたが、その途を選ばず、生きがいを全て喪失した師の枕辺で介護し、俊寛は(3日)後に安らかに亡くなるのです。
有王の師への深い思い。有王は俊寛の最後の生への執着を解き放ち、その最期のひと時を分かち合うことで、孤独からも彼を開放したといっても良いでしょう。
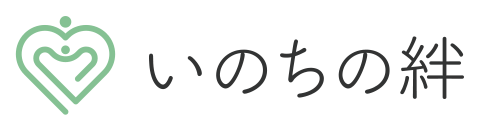



コメント