昔の読書ノートを読み返しておりましたら、次のような詩に出会い、作者のさわやかな若さに、心温まるものを感じました。といっても、作者の坂口たか子さんという方については、ほとんど何も知りません。早速、この詩を最初に読んだ紀野一義氏の『私の歎異抄』を開いてみましたが、彼女がまだ二十歳そこそこで盲目の詩人であること以外はほとんど何も分かりませんでした。彼女の詩は題して『雪の白さ』。
生まれて始めて
女である事を悲しいと思った
外は雪
いつのまにか雨からかわった雪が
すでに夜の深さだけつもっている
しんしんとしみとおる静けさが
ガラス戸ごしにつたわってくる
あつい涙を流しながら
自分を自分の外から
しみじみながめる
そこにうらみやにくしみはない
もういい
仕方の無い事ではないか
この雪の上を
はだしで歩いていったら
いつかその白さにうずもれて
雪の白さを受け継ぐことが
できるのかも知れない
愛とか出産とか、女でないと本当には分からないこともありますが、この詩もその一つでしょう。この詩の重心は冒頭の「生まれて始めて/女である事を悲しいと思った」にあるといって良いでしょう。
この詩だけでは、作者が盲人であることは分明ではありませんが、そのことが彼女の心に多大な影響を与えているとしても、それはむしろ周辺の事情にすぎません。重心はあくまで「女である事」、それを彼女が悲しみにおいて受け止めている、ということです。
ここには、乙女が女になっていくことのある喪失感というか、女であることの業の歴史があり、底辺に息づいているように思われます。それでなくとも人の心を陰気にさせる冬の雨。けれど、「いつのまにか雨からかわった雪が」が、詩に、彼女の心に転調を生み出します。無論、「夜の深さだけつもっている」雪は、彼女の心にもつもる業の深さにほかなりませんが、同時に彼女はこの心に絶え間なくつもる雪に、汚れても汚れない純潔さをみているように思われます。
紀野一義氏はこの詩に、次のような言葉を付しておりますが、まさに適切なコメントだと思います。
「雪」とは天国的なもの、浄土的なもの、仏のいのちの深さのごときものである。「夜とは人間の命の底にある「無明の闇」かもしれぬ。夜が深ければ深いほど雪も深いとは、無明の闇が深ければ深いほど、仏のいのちに生かされているのだなという思いも深くなるということである。
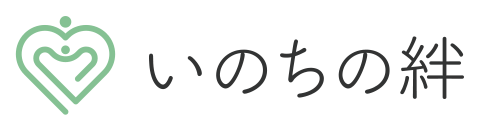



コメント